年間休日とは、読んで字の如く1年間の休日の合計数のこと。合計何日あるかは企業や雇用条件によって異なりますが、1日8時間勤務の場合、最低ラインが年間105日とされています。なぜ105日なのか、年間休日105日は妥当なのかなど、年間休日に関する疑問を紐解いていきます。
なぜ年間休日の最低ラインは105日なのか?

日本では、労働基準法第35条によって、使用者は労働者に対して、1週間に最低1回、または4週間を通じて最低4回の休日を設けることが義務付けられています。また、同32条によって、1週間に40時間、1日につき8時間を超えて労働させてはならないと決められています。
では、1日8時間勤務で週に1回または月に4回の休みの場合、年間何日休みになるかというと、1年間は52.14日なので、以下の計算になります。
1年間の労働時間:40時間×52.14週=約2,085時間
2,085時間÷8時間(1日の労働時間)=約260日
365日-260日=105日
⇒参照:労働基準法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049
年間休日105日は多い?少ない?

年間休日105日は最低ラインということは、この日数は少ないといえるのでしょうか? 1年間の週数が52.14ということは、週休2日だと年間休日104日なので、週に2日の休み以外はほぼ休みがないということになります。もしくは、お盆やお正月を休んだら、そのぶん、休日が1日しかない週が発生するということ。仕事に生きがいを感じているならまだしも、家族や友だちと2泊以上の旅行をすることも難しいとなると、しんどいと感じるのが一般的かもしれません。
年間休日数の平均は?

年間休日105日だと働き続けるのがしんどいとなると、平均的にはみんなどのくらい休んでいるのでしょうか? 厚生労働省が公表している「令和3年就労条件総合調査」の結果によると、労働者の年間休日数の分布としては、100日~109日がもっとも割合が高く、32.2%にものぼることがわかります。つまり、実際のところ年間休日105日程度で働いている人も一定数いるということになります。
ただし、企業の従業員数別に見ると、従業員数が1,000人以上だと年間休日数が100日~109日の人の割合は21.2%にまで減少。一方で、従業員数が30人~99人の企業では、年間休日数が100人~109日の人の割合は34%にものぼることから、従業員数が少ないほど、一人当たりの負担が大きくなる確率が高いといえます。
また、企業単位でみたときの平均年間休日数は110.5日、労働者ひとりあたりの平均年間休日数は116.1人と、平均値をとれば、年間休日数は105日を上回っています。
| 従業員数 | 69日以下 | 70~79日 | 80~89日 | 90~99日 | 100~109日 | 110~119日 | 120~129日 | 130日以上 | 1企業平均年間休日数 | 労働者1人あたり平均年間休日数 |
| 計 | 2.2% | 2.4% | 4.2% | 7.0% | 32.2% | 18.7% | 30.4% | 2.9% | 110.5日 | 116.1 |
| 1,000人以上 | 0.2% | 1.2% | 0.7% | 1.6% | 21.2% | 22.2% | 50.0% | 2.9% | 116.8日 | 119.7日 |
| 300~999人 | 0.2% | 1.0% | 1.0% | 4.0% | 27.7% | 20.6% | 42.4% | 3.1% | 115.2日 | 117.4日 |
| 100~299人 | 0.9% | 2.6% | 1.9% | 5.1% | 29.1% | 22.0% | 35.5% | 2.9% | 109.0日 | 110.4日 |
| 30~99人 | 2.8% | 2.5% | 5.4% | 8.1% | 34.0% | 17.4% | 27.0% | 2.9% | 109.9日 | 116.0日 |
⇒参照:厚生労働省「令和3年就労条件総合調査 結果の概況」労働時間制度 PDF3枚目より一部抜粋
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/21/dl/gaiyou01.pdf
求人情報でよく見かける「年間休日120日」は多い?少ない?

年間休日数としてもっとも見かけることが多い日数は、「120日」かもしれません。なぜかというと、多くの企業が「年間休日120日」を売りにしているからです。年間休日数が120日だと、週休2日に加えて国民の祝日も休みになる場合がほとんど。つまり、ほぼカレンダー通りといっていいでしょう。
それよりも休日が多く、年間休日が125日を超えるとなると、カレンダー通りの休みに加えて、夏季休暇や年末年始の休暇がとれるということになります。
有給休暇は年間休日に含まれる?

有給休暇は、年間休日には含まれていません。
年間休日は、「従業員に労働義務がない日」。一方の有給休暇は、「従業員に労働義務がある日に労働を免除する制度」で、いずれも法律によって付与することが定められています。
有給休暇の日数は、継続勤務年数によって決まっています。週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者“以外”の通常の労働者であれば、付与日数は以下の通りです。
| 勤続年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
⇒参照:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」より一部抜粋
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
年間休暇、有給休暇ともに法律で定められているので、当然、労働者には休む厭離がありますが、実際のところ、有給休暇が取れない、または取りにくい会社は存在します。取れなかった場合は、労務局に相談するなどの対処法をとることができますが、すんなり改善されることは少ないため、まずは有給休暇のとりやすさも確認しながら就職先・転職先を決めたいところです。
年間休日は多いほうがいい?

年間休日が少ないと、心身をゆっくり休める時間が取りづらいため、働き続けることをしんどいと感じることもあるかもしれません。しかし、年間休日は多いほどいいかというとそうとも言い切れません。なぜなら、働く時間が少なければ、そのぶん収入も少なくなる可能性が高いからです。
また、「働く日数」を減らすために1日の労働時間を長くすることで年収は保つという方法もありますが、そうすることによって、たとえば週休3日になったとしても、週のうち4日はほぼプライベートの時間を持てないとなると、それはそれでストレスが溜まりやすいことが考えられます。
長く働き続けるなら、年間休日は最低何日必要か考えよう
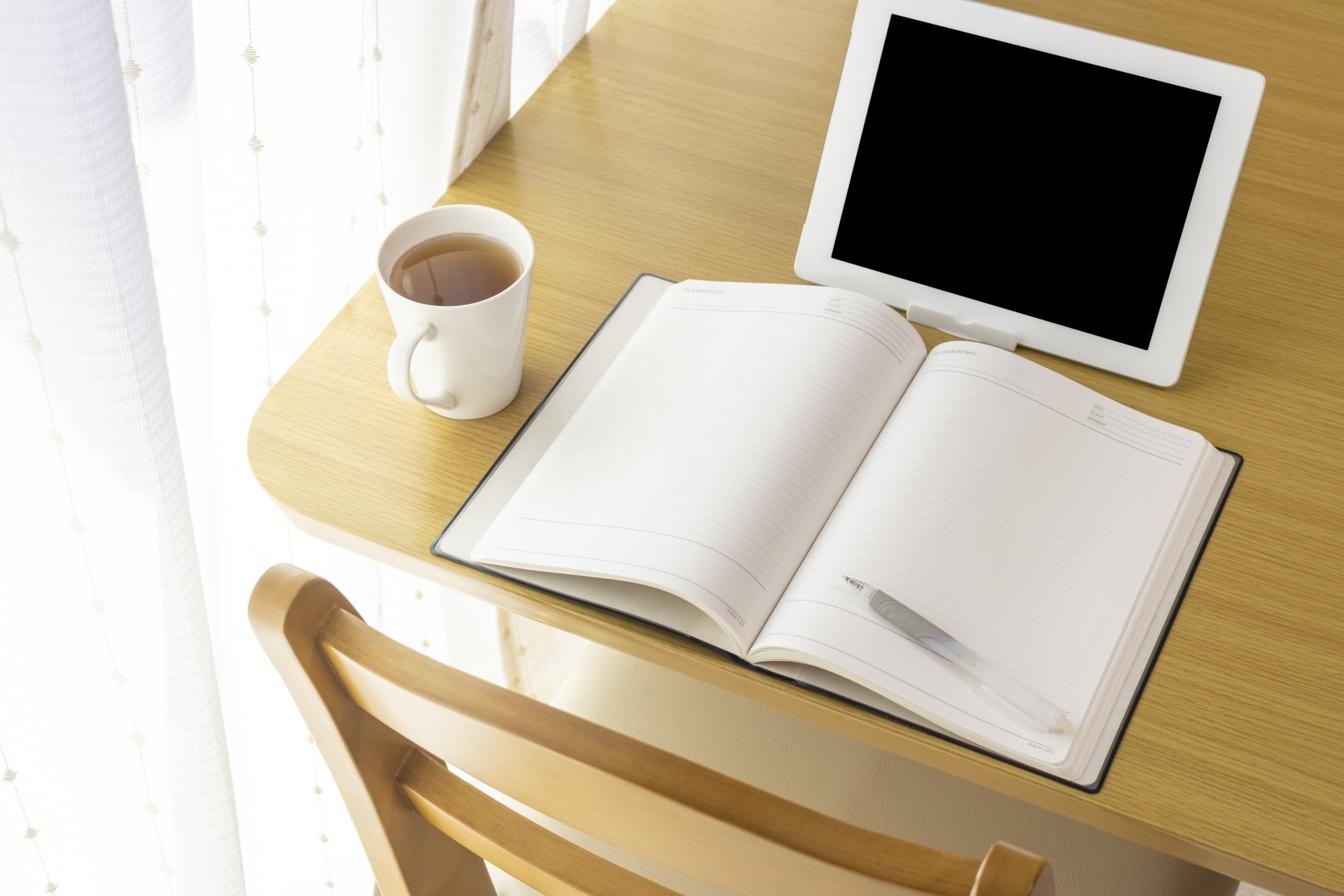
これまで説明してきた通り、年間休日105日で働いている人は一定数いますが、同じ職場でずっと働き続けた場合、来年も再来年も10年後も週休2日ということになるので、加齢による体力の衰えとともにしんどくなることも考えられます。また、ライフステージが変化していくことを考えると、たとえば子どもの夏休みに一緒に思い出を作れない、年末年始に両親に顔を見せられないなどを辛いと感じることもあるでしょう。そんなふうに、まだ見ぬ未来を想像したうえで理想の就職先・転職先を考えると、これまでとは違った条件を優先したくなることもあるかもしれません。年間休日数が平均より多いだけでなく、福利厚生も充実した企業なども探せばたくさんあるので、自分の人生をしっかり考えながら就職・転職活動を進めてくださいね。
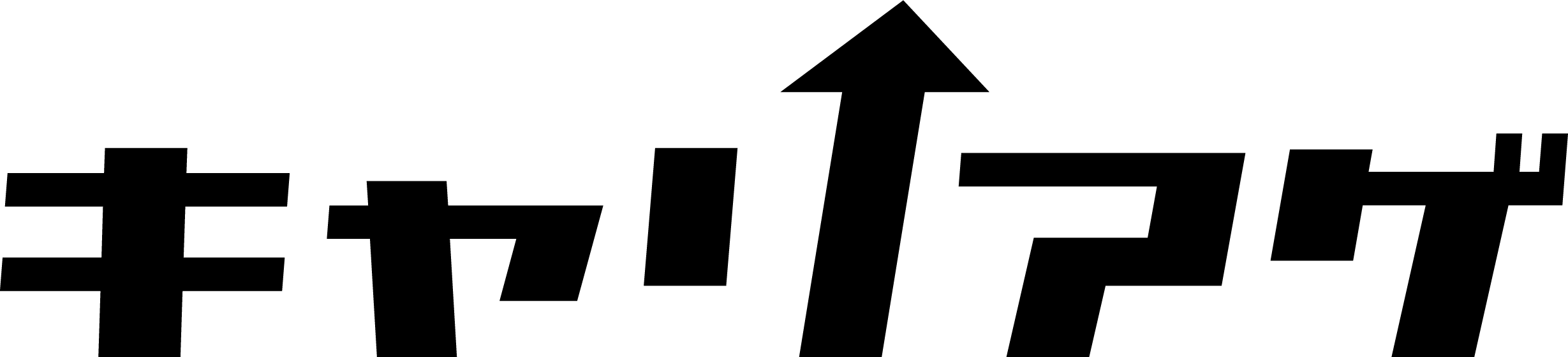


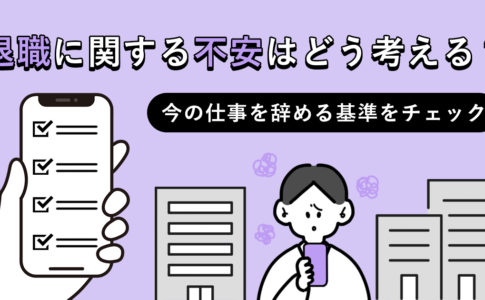

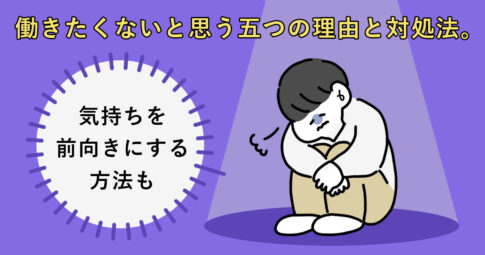






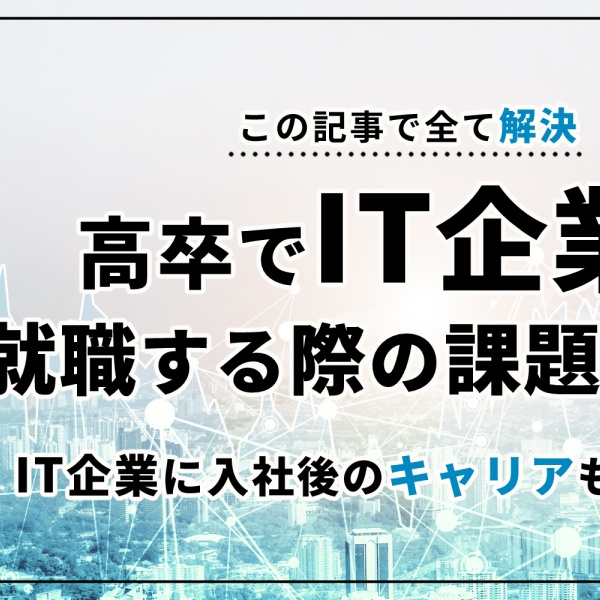


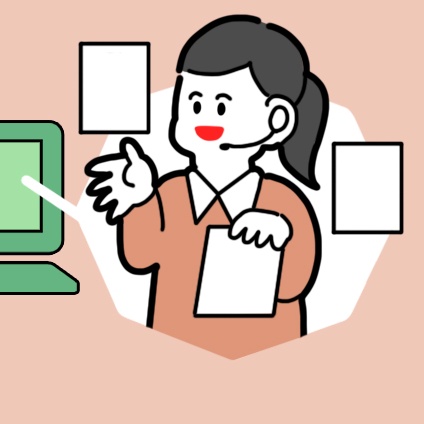
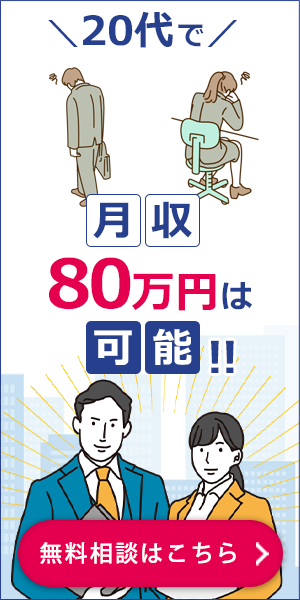
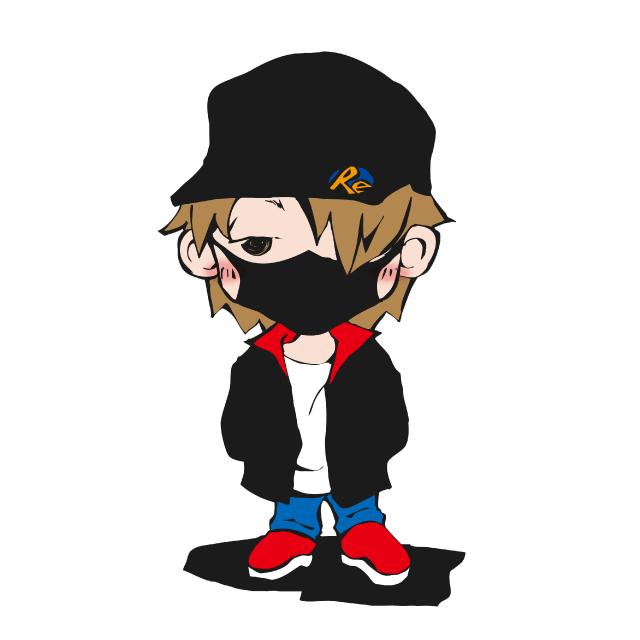

リバラボ内で1~2年間の実務インターンを行い就労実績や収入実績を積み上げ(平均年収400万円以上) インターン後の優良企業への転職まで支援するサービスです。社宅完備等の福利厚生も充実しています。
②キャリア派遣を活用してキャリアアップ
提携先(大手/上場/成長ベンチャー)企業にて社員転換を前提としたトライアル就労が可能な形態です。 期間内であれば複数の企業で実績を積むことができ、自身と企業のカルチャーマッチを 確認してから社員になれるので早期離職することなく着実なキャリアップが可能となります。
③職業紹介を活用してキャリアアップ
未経験、学歴職歴を問わず募集をしているポテンシャル採用に力を入れている企業を厳選し 貴方のキャリアを大きく飛躍するためにマッチする企業をご紹介いたします。